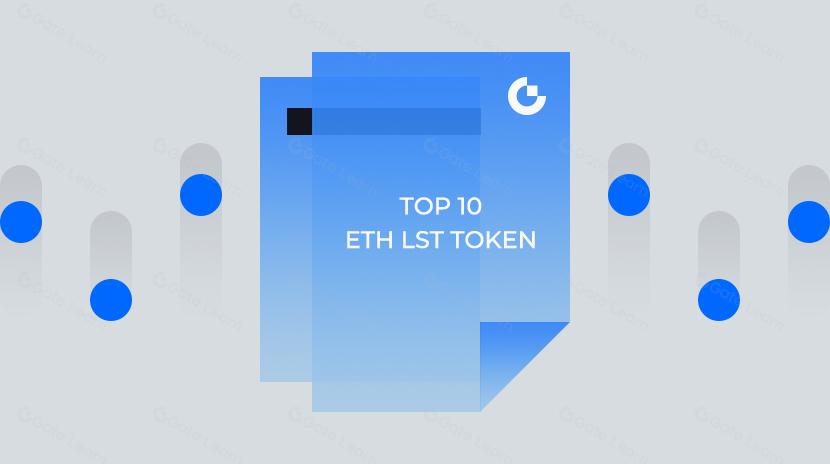EigenLayer представляє термін "Міжсуб'єктивний" як новий термін для "Соціального Консенсусу"
EigenLayer щойно випустив офіційний документ для свого протокольного токена EIGEN, представляючи численні нові та складні концепції, такі як інтерсуб'єктивний, робочий токен, форкінг токенів, слешінг за розгалуженням та інтерсуб'єктивний стейкінг. Ці терміни швидко стали предметом обговорення спільноти. Основна мета дизайну протоколу EigenLayer полягає в тому, щоб узагальнити використання вузлів Ethereum, дозволяючи цим вузлам виконувати додаткову бізнес-логіку для збільшення доходу, тим самим збільшуючи дохід для користувачів, які беруть участь у консенсусі ETH. Однак додавання такої корисності до вузлів також пов'язане з ризиками. До числа цих ризиків відносяться не тільки безпосередньо спостережувані об'єктивні ризики, але і такі, що лежать в невизначеній області між суб'єктивним і об'єктивним. Ця невизначеність, хоча і не повністю гарантована криптографією та математикою, ґрунтується на «соціальному консенсусі». Це те, що називається «інтерсуб'єктивним», яке я вважаю за краще перекладати як «соціальний консенсус».
Більше того, саме через те, що це «соціальний консенсус», протокольний токен також повинен бути forkable. Розробка моделі сегрегації подвійного токену та логіка ініціювання форків як викликів - все це частина цієї системи підтримки. Це більше схоже на впровадження логіки цілої мережі з Ethereum; вона має як (соціальний) консенсус, так і вузли, і може форкатись, але це не blockchain.
Крім того, я згадую деякі старі анекдоти, пов'язані з робочим токеном і слабкою суб'єктивністю як додатки.
Що таке Робочий Токен
Work Token обговорюється приблизно з 2018 року і став більш відомим завдяки Кайлу Самані з Multicoin Capital. У двох словах, згідно з моделлю Work Token, постачальники послуг повинні здійснювати стейкінг нативних токенів мережі, щоб отримати право виконувати роботу для мережі. Це означає, що вузли повинні надавати токени та послуги, щоб отримувати винагороду. У зв'язку з поширенням ончейн ліквідності та протоколів DeFi за останні кілька років, токени, необхідні вузлам для стейкінгу, можуть надаватися третіми сторонами, усуваючи необхідність для вузлів розміщувати великі суми власних активів. Це перетворилося на поточну модель EigenLayer: користувачі надають ETH, протокол Liquid Restaking Protocol забезпечує ліквідність, оператори вузлів надають апаратне забезпечення, а AVS забезпечує бізнес-логіку.
Зворотньо в 2018 році або раніше, галузь класифікувала токени різними способами, при цьому найпоширенішими класифікаціями були: Зберігання вартості (такі як Bitcoin), Цінність Токени, Використання Токени та Робочі Токени.
Для отримання більш детальної інформації про робочий токен та інші моделі токенів, я рекомендую почати з цієї статті від Multicoin:https://multicoin.capital/2018/02/13/new-models-utility-tokens/
Що таке Міжсуб'єктивне?
По-перше, давайте визначимо два ключові терміни: Об'єктивний та Суб'єктивний. У контексті блокчейну та децентралізованих мереж помилки можуть бути класифіковані за своєю природою на наступні чотири категорії:
- Об'єктивні помилки: Ці помилки базуються на даних та криптографії, і можуть бути чітко перевірені, наприклад, процес виконання віртуальної машини Ethereum (EVM).
- Міжсуб’єктивні помилки: Ці помилки включають соціальний консенсус серед груп. Якщо певні поведінки або судження перевищують цей консенсус, їх вважають міжсуб’єктивними помилками.
- Неподивні помилки: Ці помилки відомі лише жертвам і не можуть бути спостережені іншими.
- Суб'єктивні помилки: Ці помилки повністю ґрунтуються на особистих враженнях та поглядах, що призводить до результатів без консенсусу.
EigenLayer вважує, що неспостережені помилки та суб'єктивні помилки важко виправити, тому пропонує використовувати ETH для уникнення об'єктивних помилок та використовувати EIGEN для уникнення міжсуб'єктивних помилок.
Концепція «Інтерсуб'єктивного» може бути сприйнята як стан, що знаходиться між «об'єктивним» та «суб'єктивним». Термін складається з «Інтер» (що означає «між» або «взаємний», як у «інтерактивний» або «інтернет») та «Суб'єктивний». Таким чином, «Інтерсуб'єктивний» вказує на суб'єктивний стан, сформований між особами, консенсус, сформований у суспільстві через взаємодію.
Якщо ви запитаєте ChatGPT, що означає «Інтерсуб'єктивний», він може сказати вам важкий для розуміння китайський переклад: «互为主体性» (взаємна суб'єктивність).
Наприклад, на фінансових ринках широко відкинуте твердження “1 BTC = 1 USD” може бути віднесено до помилки міжсуб'єктивності. Тому, щоб пояснити “Міжсуб'єктивний”, ми можемо розуміти це як “соціальний консенсус”, тобто загальне прийняття певних ідей або фактів у межах групи.
Хоча в академічних та професійних дискусіях існує тонка різниця між "соціальним консенсусом" та "міжсуб'єктивним"—останнє більше акцентується на описі спільного процесу індивідуальних суб'єктивних досвідів та знань, тоді як "соціальний консенсус" підкреслює результат колективного прийняття рішень та дій.
ETH Об'єктивний, EIGEN Суб'єктивний?
Короткий огляд протоколу EigenLayer: користувачі можуть внести ETH в Протокол рестейкінгу рідини. Ці протоколи потім будуть ставити ці ETH для роботи вузлів перевірки Ethereum. Ці вузли перевірки одночасно будуть виконувати різні операції проміжного ПЗ AVS (активні служби перевірки) (такі як оракули, містки міжланцюжкові, наявність даних тощо), надаючи послуги кінцевим додаткам.

Для AVS існують два типи: об'єктивні та інтерсуб'єктивні. Об'єктивні AVS базуються на криптографії та математиці, що дозволяє чітку квантифікацію та верифікацію. У дизайні EigenLayer ці AVS можуть покладатися на переставлений ETH як їх гарантію безпеки. Натомість інтерсуб'єктивні AVS, подібні до оракулів, покладаються на дані поза ланцюжком, які не можуть бути перевірені на ланцюжку. Тому вони залежать від соціального консенсусу між вузлами; дані, визнані достатньою кількістю вузлів, вважаються надійними.
Узагальнюючи, знову вставлені ETH будуть служити робочим токеном для об'єктивного AVS в межах протоколу EigenLayer, тоді як EIGEN буде служити робочим токеном для міжособистісного AVS.
Чи можуть токени протоколу відгалужуватися?
Форкінг токенів - це новаторська концепція. Зазвичай, коли ми говоримо про форкабельність блокчейну, ми маємо на увазі його відкритий вихідний код або мережу (сам ланцюжок). У теорії токени ERC-20 не є форкабельними, принаймні не в суті, оскільки, як розумні контракти, вони повністю залежать від об'єктивних властивостей EVM (Ethereum Virtual Machine).
Однак EigenLayer пропонує, що в межах їхньої системи можливість форків токенів служить як запасний захисний захід, навіть якщо це дуже рідкісне явище. Якщо зловмисники коли-небудь стануть більш як половина мережі EigenLayer, звичайні користувачі можуть зробити форк токенів. В результаті всі користувачі та AVS (Active Validation Services) можуть вибирати відповідні токени в залежності від своєї ситуації, в суті дозволяючи соціальному консенсусу визначити, який токен є найбільш законним. Ця концепція, відома також як "вирізання шляхом форкінгу", походить з статті, написаної Віталіком Бутеріним дев'ять років тому.
Підтримка можливості розділення вимагає значної додаткової логіки. Наприклад, якщо токени можуть бути розділені, чи все ще можна використовувати EIGEN як заставу в протоколах позики? Для вирішення цього вони розробили модель ізоляції з двома токенами, де EIGEN не може бути розділений, але інший токен, bEIGEN, може. Вони також розробили процес виклику розділення та логіку компенсації для підтримки цього механізму.
Слабка суб'єктивність Ethereum
Консенсус PoS (Proof of Stake) Ethereum має концепцію, яка називається "слабка суб'єктивність," також винахід Віталіка Бутеріна, яка лежить між "об'єктивною" і "суб'єктивною." Цю властивість мають лише блокчейни з консенсусом PoS.
У мережах PoW (доказ роботи) конкуренція за обчислювальну потужність призводить до реальних витрат, що робить найдовшу ланцюг найбільш безпечною і, отже, повністю «об'єктивною». Однак у мережах PoS вартість виробництва блоків незначна, а витрати на атаки низькі. Для недавно приєднаних вузлів необхідно шукати соціальну інформацію, щоб знайти цей «слабкий суб'єктивізм». Тільки приєднуючись до правильної мережі, вони можуть об'єктивно брати участь у процесі PoS. Таким чином, деякі «суб'єктивні» фактори існують перед приєднанням до правильної мережі.
Однак, для вузлів, які вже беруть участь у консенсусі правильної мережі Ethereum, всі процеси консенсусу та операції EVM (Ethereum Virtual Machine) є об'єктивними, гарантованими криптографією та математикою. Наприклад, детермінізм введення та виведення EVM та чіткі правила для зниження випадків подвійного підпису визначені чітко.
Disclaimer:
- Ця стаття перепечатана з [ Дослідження ChainFeeds]. Усі авторські права належать оригінальному авторові [ZHIXIONG PAN]. Якщо є зауваження до цього перевидання, будь ласка, зв'яжіться з Gate Learnкоманда, і вони оперативно з цим впораються.
- Відповідальність за відмову: Погляди та думки, висловлені в цій статті, є виключно тими, хто автор та не становлять жодної інвестиційної поради.
- Переклади статей на інші мови виконуються командою Gate Learn. Якщо не зазначено інше, копіювання, поширення або плагіатування перекладених статей заборонене.
Пов’язані статті

Як поставити ETH?

Що таке Wrapped Ethereum (WETH)?

Що таке Об'єднання?

Що таке Neiro? Все, що вам потрібно знати про NEIROETH у 2025 році

Що таке Ethereum 2.0? Розуміння злиття