51%攻撃
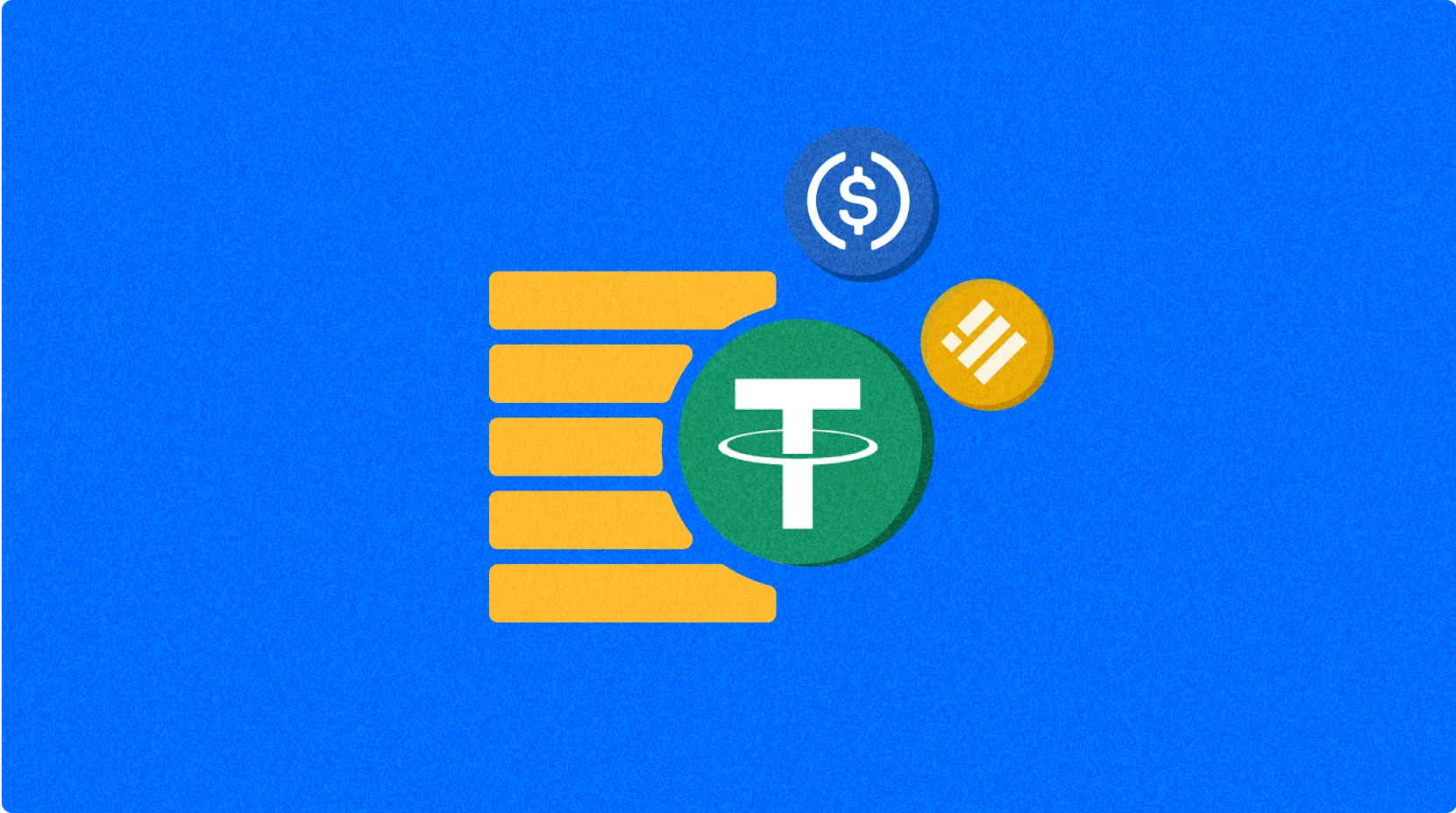
51%攻撃とは?
51%攻撃は、個人またはグループがブロックチェーンネットワークの記録保持権の過半数を掌握し、元帳の最新版を支配することで、取引の改ざんや二重支払い(ダブルスペンド)を可能にする現象です。ブロックチェーンは複数の参加者が共同管理する台帳であり、過半数の「投票権」を持つ者が自分の記録を正規とすることができます。
Proof of Work(PoW)ネットワークでは「記録保持権」は計算力(ハッシュレート)で表され、マイニング機器が解答を試みる速度を指します。Proof of Stake(PoS)ネットワークでは、保有・ステーキングしたトークンの量と影響力による「ステーキングパワー」に該当します。過半数を支配すれば、自分のチェーンが他を上回ります。
51%攻撃が発生する理由
51%攻撃は、記録保持権の集中、ネットワークのセキュリティ予算不足、ハッシュレートの一時レンタルが可能な場合などに発生します。主な目的は経済的利益、特に同じコインを二重に使って利益を得ることです。
リスク要因には、マイニングプールの過度な集中によるハッシュレートの寡占、小規模チェーンの総ハッシュレート不足で外部攻撃者がクラウドやレンタル計算力で容易に上回れること、そして少数の確認だけで商品を引き渡す加盟店の戦略が、チェーン再編成のリスクを高めることが挙げられます。
51%攻撃の仕組み
この攻撃は「最長チェーンルール」に基づきます。PoWでは、ネットワークは最も多くの作業量が積み上げられた最長チェーンを正規と認めます。攻撃者が過半数のハッシュレートを掌握すると、非公開でより長い「秘密チェーン」をマイニングし、公開チェーンを超えた時点で公開して、ネットワークに新チェーンを正規として受け入れさせます。
「チェーン再編成」は、元帳の直近のブロック(ページ)が別バージョンに置き換わる現象です。「確認数」は、ブロックがネットワークでどれだけ深く認識されているかを示し、確認数が多いほど再編成リスクは低下します。
典型的な攻撃手順は、攻撃者が公開チェーンで加盟店に支払いを行い、数回の確認後に商品を受け取る一方、同じ支払いを含まない秘密チェーンを同時にマイニングします。秘密チェーンが公開チェーンを上回るとネットワークがそちらに切り替わり、元の支払いが無効となります。攻撃者は商品とコインの両方を得る、これがダブルスペンドです。
51%攻撃の影響
直接的な影響はダブルスペンドによる受取側の損失です。その他にも、取引の巻き戻し、ユーザー信頼の低下、ノード・取引所による確認数増加、ネットワーク利用コストの一時的上昇が発生します。資産価格や流動性の低下、プロジェクトの評判悪化、開発者や参加者の離脱も懸念されます。
取引所や加盟店は、入金・支払いの確認数引き上げや、該当チェーンの出金・入金一時停止などで対応します。クロスチェーンブリッジは、悪質な巻き戻し防止のため、影響を受けたネットワークのサービスを停止する場合があります。
Proof of WorkとProof of Stakeにおける51%攻撃の違い
Proof of Workでは、51%攻撃はハッシュレートに依存します。過半数支配にはマイニング機器の投入や計算力レンタルが必要で、主なコストは機器・電力です。高いハッシュレートでブロック生成や再編成が加速します。
Proof of Stakeでは、ステークされた投票権の過半数支配が必要です。大量のトークン取得とスラッシュペナルティのリスクを伴います。多くのPoSチェーンは「ファイナリティ」を備え、一定の投票閾値を超えるとブロックが不可逆となり、不正行為者はトークン破棄などのペナルティを受けます。PoS攻撃は主にトークン経済・ガバナンスに依存します。
51%攻撃の実例
公開情報では、Ethereum Classicが2019年・2020年に複数回の51%攻撃を受けました。2020年8月には深い再編成による取引巻き戻しやサービス停止が発生。Bitcoin Goldも2018年・2020年に攻撃を受け、取引所や加盟店に損害を与えました。これらは、小規模PoWチェーンがハッシュレート集中や外部レンタル攻撃に弱いことを示しています。
2025年時点で、Bitcoinなど主要PoWネットワークは、膨大なハッシュレートと広範なマイナー分布、巨大な経済規模により、深刻な51%攻撃は成功していません。ただし、マイニングプールの中央集権化は依然として課題で、継続的なガバナンスが必要です。
個人ユーザー・加盟店が51%攻撃リスクを下げる方法
主な防御策は、確認数の増加、安全なネットワークの選択、リスク監視ツールの活用です。
- 十分な確認数の設定:確認数が多いほど安全です。GateではBTC入金は通常6回以上の確認が必要で、小規模チェーンはさらに多く(数十回)の確認を設定できます。
- 取引額に応じた段階的対応:少額決済は確認数を減らし、大口取引は多くの確認やエスクロー・クリアリング期間を設けて即時決済を避けます。
- 安全なチェーンで決済:総ハッシュレートが低いチェーンや、直近で異常な再編成があったチェーンでの大口取引は避けるべきです。
- オンチェーン監視ツールの利用:異常なハッシュレート変動やプール間ハッシュ移動、深い再編成を監視し、警告時は入金停止や確認数増加で対応します。
- 資金の安全確保:クロスチェーン送金や取引所入金では、プラットフォームの告知やリスク管理情報に注意し、必要に応じて入金を分割してリスク分散します。
プロジェクト・マイニングプールによる51%攻撃防止策
供給側の対策は分散化と攻撃コスト増加に重点を置きます。
- マイニングプール集中の緩和:小規模プールの促進、単一プールのブロックシェア制限、ブロック分布の透明開示で中央集権リスクを抑えます。
- 総ハッシュレート増加・マージマイニング:大規模ネットワークとのマージマイニングで、攻撃者がより高い総ハッシュレートを超える必要がある状況を作ります。
- ファイナリティ・チェックポイント導入:変更不可のマイルストーンブロックや再編成深度制限で、長距離再編成によるダブルスペンドを防ぎます。
- 経済インセンティブの調整:ブロック報酬や手数料分配増加で誠実なマイナー誘致とセキュリティ予算拡大を図ります。
- ノードソフトウェアの再編成ポリシー改善:異常再編成検知・警告、巨額入金の遅延、疑わしいチェーンのブロック重み減少などを実装します。
51%攻撃のまとめ
51%攻撃は、過半数の記録保持権支配と「最長チェーン勝利」ルールの悪用によって生じます。小規模PoWチェーンはハッシュレート集中や計算力レンタルでリスクが高まります。効果的な防御策は、確認数増加、安全なネットワーク選択、異常監視、コンセンサス・経済モデルの改善です。ユーザーや加盟店は、確認数管理・取引額ごとの段階対応・プラットフォームのリスク管理(例:Gateの入金確認)を組み合わせることで、巻き戻しやダブルスペンドのリスクを効果的に低減できます。プロジェクトやマイニングプールは、分散化推進、ファイナリティ・チェックポイント導入、マージマイニング、経済インセンティブ整備で攻撃コストを大幅に高め、ネットワークの耐性を強化できます。
FAQ
51%攻撃は現実に起きていますか?具体例は?
はい、51%攻撃は現実に発生しています。過去にはEthereum Classic(ETC)が2020年に複数回攻撃を受け、攻撃者が圧倒的なハッシュレートで取引を巻き戻しました。小規模なブロックチェーンはハッシュレートの分散が不十分なため脆弱です。一方、Bitcoinのような主要チェーンは正規マイニングプールがほとんどのハッシュレートを管理しているため、攻撃コストが非常に高く実行は困難です。
一般トレーダーの資産は51%攻撃で直接脅かされますか?
直接的な脅威は限定的ですが、注意は必要です。大口取引や小規模チェーンの資産保有時、攻撃者が取引を巻き戻して資金を奪う可能性があります。主要プラットフォーム(Gateなど)で主要パブリックチェーン資産を取引し、十分なブロック確認(大口送金なら通常6回以上)を待ってから資金確定することが推奨されます。これにより巻き戻しリスクは大幅に減少します。
すべてのブロックチェーンが51%攻撃に弱いわけではない理由
ブロックチェーンの51%攻撃耐性は、ハッシュレートやステーク分布によって決まります。BitcoinやEthereumは、マイニング・ステーキング参加者が多く、ハッシュレートが広く分散しているため高い耐性を持ちます。攻撃には莫大な投資が必要です。対照的に、参加者の少ない小規模チェーンは脆弱です。Proof of Stake(PoS)採用チェーンは、Proof of Work(PoW)より攻撃が困難で、攻撃者は膨大なトークン取得が必要となり、摘発時には大きな経済損失リスクを負います。
51%攻撃後、ウォレット資金は消失しますか?
資金が即座に消えることはありませんが、取引履歴の書き換えによって再割り当てされる可能性があります。51%攻撃の本質は取引記録の改ざんであり、過去の送金が消去されて資産が攻撃者のウォレットに戻ることがあります。プライベートキー自体は保持されますが、ブロックチェーン記録が巻き戻される場合があります。ハードウェアウォレットで自己管理していれば比較的安全ですが、中央集権型取引所利用時は必ず信頼できるプラットフォームを選びましょう。
Proof of Stakeは51%攻撃を防げますか?
Proof of Stake(PoS)は51%攻撃に対してより強い耐性を持ちます。PoSでは、攻撃者は全体のステークトークンの半分以上を支配する必要があり、これは膨大な経済的コミットメントです。攻撃は自らの保有資産価値を大きく毀損するため、経済合理性がありません。これに対しPoW攻撃者は比較的低コストで計算力をレンタルできるため、両機構の根本的な違いとなります。
関連記事

トップ10のビットコインマイニング会社

スマートマネーコンセプトとICTトレーディング
